Terve!
こんにちは、ロニーです。
先週末、12/1に予定していたイノシシ丸焼き会への参加ですが、
タイミング悪く風邪をひいてしまい参加見送りになりました。
1年間、ずっと楽しみにしていただけにめちゃくちゃ凹みました。
来年を待つしかないですね…。
さて、今回は資格についてです。
ITエンジニアの中では、資格有用論と無用論による対立が昔からありましたが、
弊社社長がいうには、最近風向きが変わってきたとのこと。
方向性としては、資格の有用性がより高まってきたという形です。
ITエンジニアの所属企業形態は、大別すると、
自社開発、ISer、SES、個人の4つがあります。
今回の傾向は、少なくともSESにおける意見です。
他はちょっと分かりません。
自社開発だけは依然として資格がなくても全く問題ないと思いますが、
他社から案件を受注する他3つはどれも資格に意味があるのではと僕は考えています。
インフラエンジニア、資格の重要性と無力さ
資格は取るべき?要らない?資格の意義とは。
ITの資格ってめっちゃ種類あります。
国家資格と、ベンダー資格が有名ですが、
業界団体が主催している資格や、
LPICのようにオープンソースプロジェクトがやっているもの、
更にはスタンフォード大学が提供しているCourseraのような認定証もあります。
しかし、共通しているのは、
弁護士や医師などと違って、ITは資格がなくても働くことが出来る、という点です。
なので、極論、資格が不要といえば不要です。
ではなぜ資格がこれほどもてはやされるのか。
それは、IT資格を持っていることが、
発注者に対して技術を持っていることを示す一つの指標になるからです。
仕事を依頼する側は、
依頼先のITエンジニアが、本当にちゃんと仕事をやってくれるのか、を見定める必要があります。
品質と納期を守れるのか、
支払った費用に応じた働きをしてくれるのか、
当然知りたいはずです。
そのため、自社内で社員が開発する形であれば、
わざわざ資格保持をしている必要はありません。
素直さ、学習意欲、協調性、積極性、リスクを取れるか、地頭の良さなどなど、
技術力に限らない人柄も重要ですし、
技術力は社内教育や経験値で上げることが可能だからです。
企業内文化に合わせられるかというのも、ベンチャーなどでは重要視されるでしょう。
一方で、開発・運用などの「タスク」を依頼する場合は、
基本的には最初から技術を持っている人に依頼する形になるので、
教育は度外視ですし、人柄も後回しになります。
要件を満たせるか否かが最優先で、それ以降に人柄が見られます。
この要件を満たすことを、どのように判断できるでしょうか?
まず1つ強いのは、同じ仕事や、それ以上の難易度の仕事をしたという実績です。
誰もが知っているような大手企業、例えばGoogleで働いていました、といった経験や、
みんながイメージしやすいプロダクトやサービスを開発したという実績、
例えば「日本マクドナルドのドライブスルーの注文システム作るのに携わりました」のようなエピソードがあると、同様のサービスを求めている企業にはその技術力は一目瞭然です。
直接の実績ではないけれど、自分で作ったものを見せる方法もあります。
よく投資になぞらえて「ポートフォリオ」と呼ばれますが、
自分の作った作品や携わったプロジェクトをまとめたものをそう呼びます。
WebサイトやWebアプリであれば、自分の端末なり公開しているIPアドレスやURLなりを見せられれば、それがそのまま説得力になります。
そして最後に、IT資格です。
実績や作品が直接的に技術力を示すものとすれば、
資格は間接的に示すものです。
作ったり動かしたりすることを示すのではなく、
作ったり動かしたりするやり方を知っていることを示すものだからです。
こういった理由から、
「実績、実力があれば資格は要らない。」という見方はとても強いです。
実際、それは間違っていません。
しかし重要になってくるポイントは、
実績がない場合はどうやって仕事を振ってもらうか?
実力をどのように示すか?
という部分です。
実績がない場合と、
実力はあるけど伝えることにハードルがある場合には、
資格が一つの指標として求められがちなのです。
以降の項でその2点について話しますが、
その前提として、仕事を取ってくる現状を把握しておきます。
IT業界を取り巻く状況
企業が、何かアプリケーションを作りたがったり、それを動かす人が必要だとします。
そのために、開発する人、運用する人を見つけたい。
大規模なアプリだと100人規模とか普通にあります。
DXが喫緊の課題でもある現在は、多くのエンジニアが必要とされます。
更に一度開発してしまえば終わりではなく、
新機能追加したり、不具合を直したり、
使いやすく改修する必要があるので、開発者も継続的に必要になります。
使うユーザからの問い合わせに対応したり、
アプリを構築する各種技術にアップデートが入れば、
それに合わせて更改する必要もあります。
OS、ミドルウェアなどあらゆるフェーズで各パーツが古くなっていきますが、PCみたいにアップデートボタンをぽちっとして再起動すればOKというわけにはいきません。
それによって、そのパーツの上で動いているアプリに不具合が発生して動かなくなることがとても多いからです。
ITエンジニアはかなり不足しているとされています。
(Yahoo!ニュースのリンク)
約7割が「IT人材ゼロ」…日本のIT人材不足が深刻化。経産省が予測する“2030年までの未来”【経営者アンケート】
2016年に経産省がIT人材の不足を示した情報がよく引用されますが、
新しい資料としてすぐ見つかるのは上記のアンケート結果でしょうか。
ITエンジニアが不足している、とはいうけれど、
実際に求職や案件探しをしてきた身としては、
不足しているのは「即戦力」となる、ハイスペックなITエンジニアです。
需給バランスからITエンジニアの給与水準は他業界と比べて高い傾向がありますが、
その中でも特に目立つ高単価のポジションや、自由度の高い働き方というのが喧伝されてきました。
確かにそういった企業や案件はありますが、規格外に倍率が高い。
どの時代にも超優秀なITエンジニアは存在するので、
そういった連中が大体収まるべくして収まっているように思います。
その一方で、条件は良くないけど、働き場所としてはある、という企業や案件が山ほどあります。
ずば抜けて優秀ではないITエンジニア達と、
新天地を求めて異業種からやってきた新米エンジニア達が、
そのポジションでほど良いところを目指して切磋琢磨しているわけですね。
1つの案件で関わる技術というのは、そこまで広くありません。
なので、仮に1年から3年、同じ現場で同じシステムに関わっていても、
そのシステム以外に移ったり、それまでの担当範囲から外れたりすると、
他の技術についてはまた学び直しになります。
0とか1からスタートというわけではなくとも、
経験値はかなり低い部分から再度積みなおす形になります。
これが結構厄介なんです。
僕はこれまで、ITの基礎力があれば、別の担当範囲や別のシステムでもすぐ対応できると思ってました。
いや、今でもそうだと思います。
しかし発注側はそうみなさないようです。
サーバーエンジニアがWebアプリ開発に移ったり、
クラウドエンジニアに移ったりという横移動は、
ほぼ異業種転職に等しい扱いを受けます。
多分Webデザイナーがネットワークエンジニアに移るとか、
データベースエンジニアがモバイルアプリエンジニアに移るといった動きも同じなのではないでしょうか。
エンジニアを抱える企業や発注する企業は、
人材をじっくり現場で育てようとする気がないか、
その気はあっても金銭的に余裕がないのでしょう。
コストかけて育てたところですぐ転職されたりしますし。
そうなると、とにかく「実績がある人だけが今すぐ欲しい」という形になります。
実務経験のない新米エンジニアが飽和しているのに、
IT人材が全く足りていない、という今の現状がこれです。
その他、大手テック企業が大規模レイオフしてスキルのあるエンジニアが急にワッと出てきたり、
新米ITエンジニアを量産するプログラミングスクールの跋扈や、
ベテランだろうが新米だろうがマッチングさせてマージンを稼ぐ人材斡旋業を猫も杓子も行っている現状が、さらにこの状況を助長しています。
「やりたい業務経験をなんとかして積んでより良いポジションを目指したい」
という経験不足のエンジニア達と、
「育ててもすぐに辞めていくからやっていけない」SES企業と、
「低品質のITエンジニアを何とかふるい落として、
何も言わなくても自主的にいい成果を出してくれる則戦力エンジニアを確保したい」
という発注企業のせめぎ合い。
これが縮図といえそうです。
実績がないITエンジニア、実力を伝えられないITエンジニアのための、資格取得
前項で書いた現状の中で、その意義を示してくるのが、IT資格となります。
ある意味、苦肉の策でもあるといえます。
実績を持ちたいけど持つ機会がない、
だからひとまず資格を取って、関連技術に関する知見をアピールする。
実力はあるけど、間に技術的にあまり詳しくない営業・採用担当者が挟まることによって、
現場側の求める人としてピックアップされにくい、
だから誰が見てもすぐ判断できる資格によって知見をアピールする。
こういった状況が考えられます。
なので、実績、つまり実務経験や目に見えるポートフォリオには及ばずとも、
資格を持っていることも、確かに武器の一つとなるわけです。
ただしここで追加で問題になるのは、
誰もかれもが資格を取得できてしまっていることです。
新米エンジニアが飽和している、と前項で書きましたが、
そんな新米エンジニアがこぞって資格を取得したことから、
「基礎的な資格は持っていて当たり前」になっているのが現状です。
仕事に応募したしたときに、
ある特定の資格を持っていないとふるい落とされるとか、
資格を持っていても「ふーん」くらいにしか思われなくなってしまっているようです。
僕個人でいえば、
今はクラウドエンジニアのポジションを得るためにAWS資格を順に取っていますが、
最低でもアソシエイトレベルの資格を保持していること、というのが必須条件になっている案件があり、
改めて資格取得を目標に定めるきっかけになりました。
しかし今僕はAWS認定ソリューションアーキテクト-アソシエイトと、
同SysOpsアドミニストレーター-アソシエイトと、2つのアソシエイトレベル資格を保持していますが、
それでも未だクラウド案件の面接にたどり着けずにいます。
ネットで検索すると、いわゆる「全冠」と呼ばれる、
AWS認定資格11~13個程度を全て取得している猛者もゴロゴロいます。
(AWS認定資格は新しいのが出たり統廃合したりするので年によって総数が増減します)
弊社の社長曰く、
「資格はなくても問題ないけど、超強いエンジニアは大体資格を持ってる」。
ITでは常日頃ググって技術について調べているので、よく見る技術ブログってのがありますが、
僕がひそかによく見て参考にしていた、Side-Bさんっていうインフラエンジニアは、
プロフィールを見たら僕が欲しい資格を総なめしていて恐れ入りました。
以前一緒に仕事した某Jさんも然り。
資格を提供している側としても、
資格としての意味を無くしては意味がないので、
資格の価値が下がらないよう、
数年ごとに取り直さないと失効してしまうケースが増えています。
また、試験の難易度も、テキスト比較すると新旧で大きな差があることが散見されます。
AWS資格ではそれが顕著。
年々、中高大学受験でもどんどん早期化、高難度化している傾向があることを考えると、
今後も資格取得の戦い、資格取得者同士の戦いは激化していく気がします。
基本的な資格は、早期に取っておいて、適宜アップデートする。
基本的な資格とは別の形で技術力を示す戦略を練る。
この辺が今後のスタンダードではないでしょうか。
おわりに
ここまでインフラエンジニアとして、
IT資格の重要性と、その無力さを同時に語ってきました。
仕事で学べる量は、自己学習や研修で得られる量をはるかに凌駕します。
まさに、百聞は一見に如かず。
資格取得も、ポートフォリオ作成も、
自己学習も自分を確実に伸ばすものですが、
それだけでは則戦力になるのは不足だと思います。
資格学習には、技術の全体像を網羅して体系的に理解できる、
という大きなメリットがあります。僕はこれこそが資格の一番大きい利点だと思っています。
実体験からも、その体系的理解は仕事に確実に活かせるものだと信じています。
が、そもそも仕事を得る、という点では、
資格はまだまだ威力不足なのは否めないでしょう。
そうなると最終的には、
「自分でゼロから、またはイチから仕事を生み出す」ことも必要になるんじゃないでしょうか。
自分でアプリを作成して直接収益を上げるとか、起業するとか。
インフラエンジニアにも、開発力と営業力が求められている時代なのかもしれません。
まだまだ道筋が見えない昨今ですが、
資格と実績(実務経験)を両輪としてパーツを揃える、というマインドで進んで行くつもりです。
今回は以上!
モイモイ。
(おまけ)
以下に、ITエンジニアとしてのキャリアやスキルアップに関して参考になる書籍を挙げておきます。
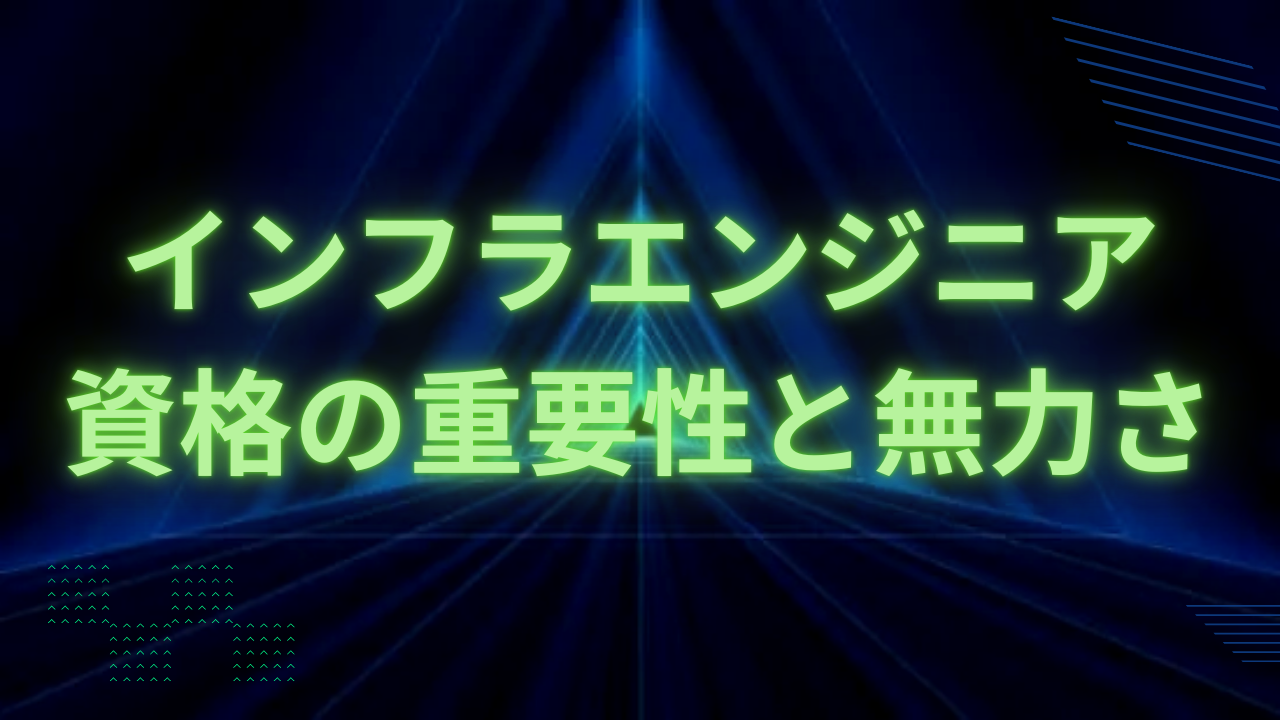



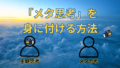
コメント