Terve!
こんにちは、ロニーです。
クリスマスももうすぐそこですね!
だというのに全然クリスマスらしいブログを書けていないから、次回書こうかな。
さて、仕事と私事の両面で「師走」を感じている昨今。
前からビジネス書や心理系の書籍などで触れていた「メタ思考」を、
改めて意識的に鍛える必要性を感じています。
でもメタ思考って、どうやって身に付ければいいのだろう?
メタ思考に関係する本などを読んだりする機会が増えたので、
改めてメタ思考について簡単に説明した上で、
僕なりに「どうすればメタ思考を身に付けられるか?」、
その仮説を立ててみます。
ちなみになぜメタ思考がいいのか、という話は、
あちこちの本やWebサイトで語られているので今回は触れません。
いってみましょう。
「メタ思考」を身に付ける方法
メタ思考とは何か
「メタ思考」とは、メタ認知を活用した思考法です。
メタ認知というのは、俯瞰的・客観的に自分自身を認識する能力です。
自分の思考や言動や癖、感情などを、第三者目線で見据える見方と力、とも言い換えられるでしょう。
この能力を活用して、
その後の具体的なアクションに繋がる考え方を、メタ思考と呼んでよいと思います。
まずメタ思考について考えてみましょう。
メタ思考とはどんなものなのか。
人は前提として、物事を主観的に見ます。
例を挙げれば暇がないのですが、
我が家で毎日繰り広げられている育児の場面から一つ。
俺「ご飯の途中だぞ。遊ばないで食べるのに集中して」
子「今電車がここ走ってて忙しいだから。ガタンゴトーン」
俺「ご飯中だって言ってるでしょ、遊びたいのは分かるけど、食べてから一緒に遊ぼうよ」
子「でももうお腹いっぱい」
俺「まだ全然食べてないじゃん!昼ご飯だってまともに食べてない。朝も」
子「熱いから食べれない」
俺「もう完全に冷めてるよ!もし熱ければフーフーすればええやん」
子「熱いからまだ食べられない!!それに寒いし。寒い寒い。服取ってこよう」
俺「言い訳ばっかりしてるんじゃない!」
うちではコニーがいつも全然ご飯を食べようとしないので、
こんなやり取りが毎日毎食、発生します。苦行です。
こういったとき、メタ認知では自分の頭の中にフォーカスします。
(以下、ロニーの頭の中)
食べて欲しいのに全然食べなくてイライラする。
昨日から全然食べてもらえてない。一昨日も本人のリクエストに応じて作ったのに食べなかった。
食事は美味しくて楽しくて普通待ち遠しいものなのに。
ん?「普通」ってことは、俺にとっては「ご飯は楽しいもの」って考えがあるわけだな。
俺のその前提と状況が一致しないからイラつきを感じるのかもしれない。
コニーにとっては「ご飯は楽しくない」のか?
俺が「ご飯は楽しいもの」と思うのはなぜだろう。
コニーにとって「ご飯が楽しくない」のはなぜだろう。
過去の食事時の楽しい思い出の蓄積の差だろうか。
確かめてみよう。
(後略)
こういった感じで、自分自身の行動や気持ちを俯瞰的、客観的に見ます。
これがメタ認知。
メタ認知だけだと、まだ自分についての気づき止まりです。
メタ思考に加えて、
環境や状況、応対する他者の考えなど、直接的に見えないものまでをまとめて、
「メタ」的に行おう、俯瞰的に見よう、というのがメタ思考です。
普段、仕事でもプライベートでも、我々は様々なことを考えてますが、
ついつい思い付き、反射神経、慣性で発言したり行動したりしてしまいます。
これだとどうしても浅い。
ミスを減らしたり、深い仮説を立てたり、人を思いやった言動を取ろうとするのであれば、
メタ思考をワンクッション挟むことで改善が期待できます。
メタ思考は実践が難しい!
メタ思考は行うのが難しいです。主観的な思考と比べて。
主観的な思考は、直観的ですぐに動けるものだから、
認知、即行動、という方が動物的には自然ですし、頭を使わないのでラクです。
僕はメタ思考をする上でのハードルは2つあると思っています。
1つ目が、メタ思考中は主観の行動を自動化する必要がある
2つ目が、感情がメタ思考の邪魔をする
1個ずつ見ていきます。
メタ思考中は主観の行動を自動化する必要がある
人は自分の行動などを俯瞰的に見るとき、自分の手元などから集中が外れます。
人間は本質的にはマルチタスクは出来ないと言われています。
複数のタスクをマルチに行うためには、
高速で個別のタスクを切り替えて同時に行っているように見せるか、
もしくは一部のタスクを何も考えずに無意識下で行って、
その上で意識的に何か別のことをする必要があります。
例えば料理する時には同時に色々なことをしますが、
スパゲティをかき混ぜながら、
フライパン上のソースを混ぜながら、
具材を切りながら、洗い物をする、というのを全く同時にしているわけではありません。
天津飯やゴーリキーでも難しいと思います。
こういったマルチタスクは、実際には素早く複数のタスクを捌いているケースです。
一方、同時に行動するマルチタスクも存在します。
車を運転するときには、
アクセルやブレーキを足で踏み、
両手でハンドルやギアや各種レバーやボタンなどを操作し、
周囲の人や車、それに信号機や制限速度や走行車線に意識を割きます。
その上でこの先の道を考えたり、同乗者と会話までしちゃいます。
信じられないほどのマルチタスクです。
僕みたいなペーパードライバーだと頭がパンクしちゃいます。
慣れている人なら全部に意識を向けなくても、
その時その時の重要なポイントだけに集中して、
それ以外はオートマティックに操作できます。
無意識に色々なことを出来るようになるには、どうしたらよいでしょうか?
無意識でも行動できるようにするためには、
反復によって動きや流れを身体に覚えさせる必要があります。
もちろんこれも完全に頭を使っていないわけではないけれど、
その割合が非常に小さかったり、反射神経的に実施したりすることで、
その分の脳内のスペースを別のことに割り当てられるって寸法です。
上記の2点から、
マルチタスクをするためには、
全体像を把握した上で、素早く正確に思考と行動を切り替えるか、
無意識でもできるように練習して身体に覚え込ませ、
かつ意識のスポットライトを柔軟に動かすための技術が必要になります。
脳と体を高度に使っているのが分かります。フル活用です。
さぁやろう、と思って出来るほど簡単ではありません。
トレーニングが必要です。
その都度、意識を当てる対象を切り替える、
というのもコントロールを要しますし、
自転車、車、ドラム、ピアノなど、頭と四肢をバラバラに動かすのにも、
コントールを要します。
そしてさらに、心技体でいえば「心」の部分、
つまり精神面、感情もコントールが必要です。
感情がメタ思考の邪魔をする
人は感情的になると、目の前のことしか考えられなくなります。
進化の流れを考えてみても、
差し迫った危機などに迅速に対応して生存確率を高めるために、
恐怖や怒り、好意、緊張など様々な感情が構築されたと考えられます。
だから感情的になった時に、細かい周りのことや先のことが考えられなくなって、
場当たり的で自己中心的な行動に陥るのは自然なことだと思います。
従って、メタ思考のように、俯瞰的・客観的に思考するためには、
まず感情をコントロールし、欲望や不安定な心情を一旦脇に置いておくスキルが必要になります。
メタ思考のために落ち着いて自分の考えにスポットライトを当てないといけないのに、
そもそも頭がパニックになってそういう気にもならない…。
これじゃ先に進みませんからね。
感情をコントロールするには
心と身体はお互いに影響し合います。
緊張してれば身体は動きにくくなるし、
風邪をひいたりして身体の調子が悪ければ、テストでいい点を取るのは難しい。
感情も然りで、
やりかけの仕事が頭から離れないとか、
寝不足で身体が重いといった状態では、イライラしたり落ち着かなったりします。
なので、感情を落ち着かせるためには、
やるべきことを事前に終わらせるなどして時間に余裕を持たせたり、
体調を整えることが必要になります。
当然、万全にするのはかなり難しいはずです。
その時点でのベストコンディションであれば充分でしょう。
もし感情が波立って仕方がないとすれば、
まずはやるべきことをさっさと済ませて時間に余力を作る。
そして睡眠、食生活の見直し、運動、掃除、瞑想、サウナ、深呼吸など、
なんらかの手段で心身を整えるのが近道です。
健康法、ストレス解消、集中力の高め方、禅、アンガーマネジメント、筋トレなど、
心身を整える仕方を教えてくれる情報はいくらでもあるので、
自分に合ったものを探してみるといいでしょう。
欲望をコントロールするのはまた非常に難しい話なので、
ここでは割愛します。
メタ思考を「空間的」「時間的」「複層的」な視点で捉える
さてじゃあ、メタ思考を行う具体的な方法についてみていきましょう。
状況や考え、物事を俯瞰的に見るにはどうしたらよいでしょうか?
ビジネスであればフレームワークなど便利なツールがありますが、
まずは軽いイメージから始めるのが分かりやすいかと思います。
イメージ(想像)をしてみることで、
意識の当たっている部分を、勝手に動く身体・行動面から、脳内に切り替えられるからです。
俯瞰的な視点は、幽体離脱のイメージ。
自分の視点を天井に持って行って、
今の自分を頭上から見下ろすのをイメージする感じですね。
物理的に、今の自分の立ち位置を把握できます。
僕がバンド活動をしていたとき、
全体を俯瞰的に見るために、
自分の意識をステージの背景の幕とか照明がぶら下がっている位置に設定していました。
こうするとステージ上の自分とメンバーに加えて、
フロアやPA席までを把握しやすくなるんです。
ただこれはまだ視点だけなので、息遣いとかグルーヴまでを感じ取るためには、
もう一歩別のイメージを持ってました。
それは、自分の身体の表面感覚や操作性を膨らませて、
球状にオーラを広げて、空間全体を包み込むイメージです。
ハンター×ハンターでいう「円」を球体にした感じ。
自分を取り巻く環境をふわーっと大まかに捉えるわけです。
流石に現実はファンタジーの世界じゃないので、
意識を広げただけで実際に物事の位置や質感などを実際に得ることはできません。
イメージではなく、実際に見える範囲をメタに見るとなると、
こちらは意味合いとしては剣道でいう「遠山の目付」というものに近くて、
「木を見て森を見ず」という言葉のうちの、森を見る見方と共通します。
視野の内の一点に集中するとそれしか意識に登らなくなるわけですが
この空間的なメタ思考の視点では視野全体に意識を分散するので、
正確性を犠牲にして、全体における動きや変化への気づきを得られるようになります。
僕の経験では立体視、間違い探し、ウォーリーを探せなどでめっちゃ活かせます。
今紹介したのは空間的なメタ思考ですが、
時間的なメタ思考もあります。
自分の行動のその先や、行動・感情を決めるに至った過去の経緯を考えるのが、
時間的メタ思考です。
(未来)
自分がこう言ったら、相手はどう思うか。
自分の5年後には考え方がどう変わっているだろうか。
自分の臨終のとき、自分の近しい人はどのように思うか。
(過去)
自分のこの癖は、どういう経緯で習慣化したものなのか。
自分と親兄弟の性格の差はどこから生じているのか。
自分のこう考えるようになった契機はなんだったのか。
なぜそうなのか、これからどうなるだろうと、
色んな物事に対して頻繁にWhyを持つことで、
対象と時間との関係性を考える習慣が付きます。
自分自身を、時間と空間の両面から考えるのに加えて、
自分以外の対象との、時間的・空間的な関係性に思いをはせてみると、
また違ったものが見えてきます。
これを僕は複層的なメタ思考、と捉えています。
時間と空間をx軸とy軸と捉えれば、
「主体」を3次元のz軸と置けます。
この主体は自分や自分と話す相手でもあれば、
物や国や制度などどんな対象も当てはめられます。
相手の言動や性格は、何が影響して構築されたものなのか。
このモノ、この国はどういう経緯で今に至っているのか。
なぜ今人間はこうあり、なぜ法律はこうあり、
また未来の人間や法律は、世界はどうなっていくのか。
このように、
主体を変えて様々な目線で物事を考えてみるのが、複層的メタ思考だと思います。
空間的でも時間的でも複層的でも、
認知してから行動するまでのフローは共通します。
イメージをしてみる。これは想像です。
そこから仮説を立て、検証へと進みます。
こんな気がする(想像)
→なぜこうなのだろう(疑問)
→こうかもしれない(仮説)
→試してみよう(検証)
想像~仮説までは全部頭の中でしかないので、
メタ思考が出来てもアクションに繋がりません。検証してこそ、
メタ思考に価値が生まれます。
メタ思考を身に付けるために、使い倒す
上の項で、メタ思考には空間的、時間的、複層的なメタ思考があると書きました。
ではそれぞれを身に付けるためのトレーニングを考えてみましょう。
空間的なメタ思考を身に付けるのには、
僕は瞑想と運動がいいのでは、と考えています。
瞑想って色々あるけれど、
僕がここで考えているのは、自分の身体の各部位に意識を向ける行為です。
自分の姿勢や重心、身体をまとう風や温度感などを、
意識的に感じてみると、自分が物理世界に存在する物体の一つであることを感じられます。
座っている床の硬さ、太陽の熱、光の強さ、
そういった感覚が、自分と世界との関係性を強く感じさせてくれます。
この意識の距離感を少しずつ遠くしていくイメージです。
僕がよく想像しているのは、
電車内で立っているときに、同じ車両の端っこから反対端までを、
自分の体温で包む混むような想像です。
この気持ちは言語化しにくいけど、なんか面白いです。
瞑想に並ぶもう一方、運動ですが、
こちらはマラソン、筋トレ、スポーツ、格闘技。なんでもいいと思います。
身体をどう動かすかをよく知ると、
それだけ自分と世界との関りを感じやすくなるからです。
運動は身体も整うので感情コントロールにも繋がります。
時間的メタ思考を身に付けるには、
物事の因果関係をロジカルに考えてみるのがいいでしょう。
因果関係を知らなければ、まずは自然科学について学ぶのがとても役に立つと思います。
僕は地学や歴史、国際関係論、物理学、心理学、遺伝子学、脳科学などが好きですが、
物事が「なぜ今そうなっているのか」という原理を知ることで、
世界の解像度が上がって色々なものがクリアに見えてくるんですよね。
因果関係が分かると、物事の過去と未来のつながりを理解しやすくなります。
そもそも物事の成り立ちを詳しく知らない場合ですが、
その場合は仮説を積み重ねる形になります。
想像上ではありますが、
こうなんじゃないだろうか、という色んなルートの関係性を、
論理が破綻しないように脳内で積み重ねます。
そんな中で、これまで見えなかった関係性にハッと気づくことが結構あるものです。
仮説←→検証を多くループすることで、
あらゆることの時間的な関係性を捉える力が身に付きます。
複層的メタ思考のトレーニングについて。
これは時間的メタ思考と重複しますが、
遺伝子学や心理学、そして社会学や民俗学を学ぶと、
他の人がどう考えているかを想像しやすくなります。
自分とは全く違う考えを、相手の立場だったらどう考えるだろうか、
と想像してみる。
でも全く違う考えなんて知らなければ当然理解できないので、
そのために人間の考えの仕組みを学ぶのが役に立つわけです。
ただ重要なのは、それはあくまで自分の想像上の他者の気持ちや考えなので、
自分の想定が正解ではないということ。
自分の考えと全く違う可能性があることを分かった上で、
相手の考えを仮定してみるわけです。
「こう考えるはずだ」と決めつけたり、
自分はこう考えるから相手もこう考える、
自分の回りの人はこう考えるから相手もこう考える、というのは決めつけになるので要注意。
主観的思考から抜け出せていません。
生理学上、統計上、人はこういう考えや行動を取るとされてる。
それをベースにして、
この人がこうしたのは、こういう考えからじゃないだろうか?
この人がこう思ったのは、こうだからじゃないだろうか?
と仮説を立ててみます。
それについて本人に聞いて確かめてみてもいいですし、
その後の動きを観察して可能性の裏付けを自分の中で留めておくだけでもよいでしょう。
それによって充分、誤解による失敗を減らせます。
さてこうしたメタ的な思考を、
平生の、上司や同僚やお客さん、家族との会話の中で、
また布団の中や電車の中や歩いている中で、じっくり考えてみる。
この機会を多く持てば持つほど、トレーニングになるものと思います。
おわりに
時間的メタ思考、空間的メタ思考、複層的メタ思考のほかにも、
きっと想像外の世界があるでしょう。
僕は適当に3次元的にそう設定してみましたが、
次元は超ひも理論的には11次元もあるわけですし、
他にも色んな視点を想定できます。
例えば匂いとか、
色合いや音のような周波数とか、
温度、変動率、確率とか。
もはや「視」点ではないですね。
まずはそれぞれの思いや感覚を感じたり想像してみる。
そしてそのメタ思考を何度も使って、トレーニングする。
メタ思考を習慣化することで、
必要なときに瞬時に引き出せたり、
無意識にもメタ思考を使えるようにすることができるのではないでしょうか。
メタメタな人間になって主神オーディンのように世界を見通せる力を得たいものです。
今回は以上!
モイモイ!
(おまけ)
以下に僕が最近読んで上記のような考えを持つに至った参考書を紹介します。
※近日読もうと思っている関連本も他にあるので追って追加するかもしれません。
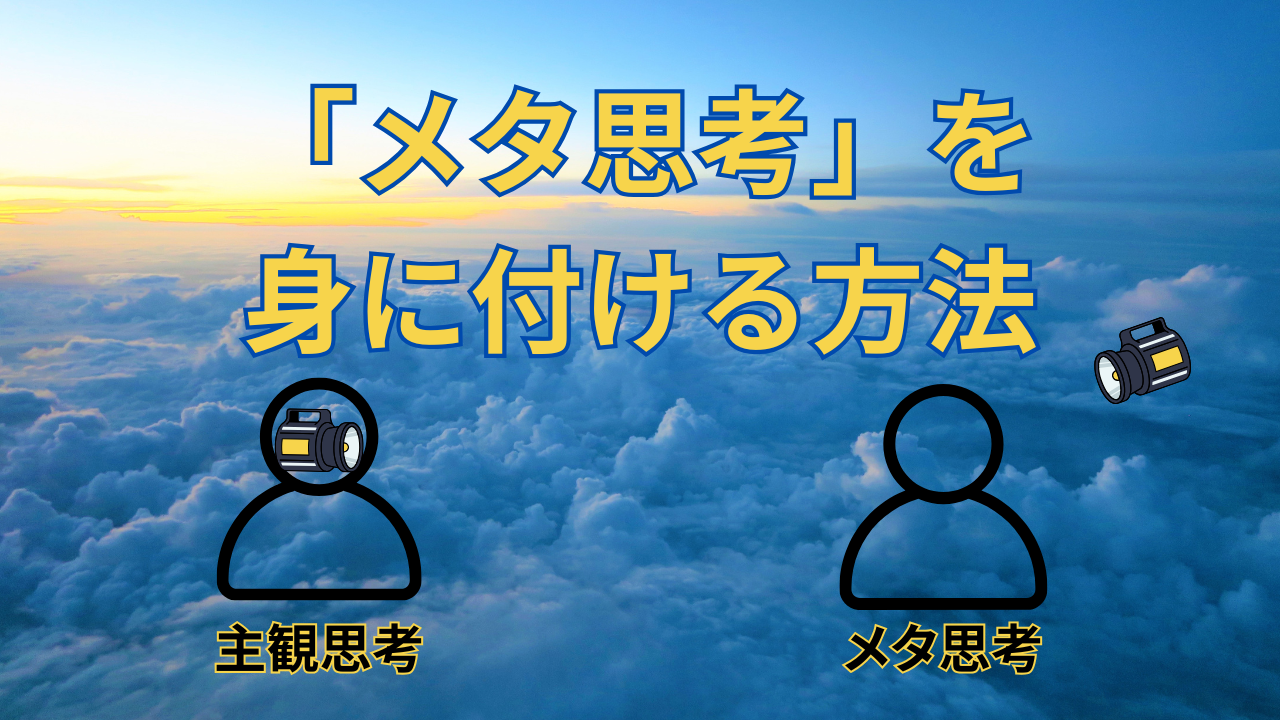




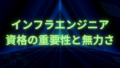

コメント