Terve!
こんにちは、ロニーです。
昨年もお邪魔した、
飯能・青梅間にあるエアビー宿の風土舎ハクナマタタに、先日宿泊してきました!
1年間ずっと楽しみにしていて、待ちわびていたこの時。
昨年末の「イノシシ丸焼き会」はコロナ感染してしまったため参加できず、実に1年以上ぶりの訪問です。
この風土舎ハクナマタタはAirBnBにも登録されている、
築約150年の古民家を改装した宿泊所です。
前にAirBnBの公式サイトで調べたときには、
中々検索ヒットしなくて見つけにくかったんですが、
オーナーの野口さん曰く、
「本当にここの雰囲気が大好きな人へのオススメとして表示されるから、
来る人みんな感動してくれる」とのこと。
パーソナライズアルゴリズムについては
普段ネガティブな面ばかり感じてしまいますが、
正の側面、技術の恩恵ってこういう部分ですよね。
風土舎ハクナマタタにお邪魔したブログについては過去にも何度か挙げているので、
今回は特に紹介的なことは書きません。
2020年以降、爆発的に進展した生成AI技術が、
2023年末頃からさらに加速しました。
ここまで急激に浸透するとは正直想像していませんでした。
私自身は生成AIを活用つつも、
そのリスクをひしひし、いやビシビシ感じています。
生成AIによって仕事と生活がどうなると予想されるか。
特に、僕の仕事であるシステムエンジニア職と、
妻の仕事であるデザイナー職の目線で考えていきます。
今回ハクナマタタに行って改めて気づかされた部分があったので、
その辺の考えについても書きます。
AIによる仕事の変化 ~SEとデザイナー~
AIはITエンジニアの仕事をどう変えるか
僕は今はシステムエンジニアをしています。
キャリアのベースにインフラエンジニアがあって、
その上にPythonとフロントを組み合わせたアプリ製作、システム設計、
そしてDBの構築が小規模ながら乗っかっている、
フルスタックのシステムエンジニアをしています。
生成AIのITエンジニアリングへの活用法は色々ありますが、
最もインパクトが大きいのはコーディングをお願いできることでしょう。
VSCodeの拡張機能で使えるCopilotやClineや、
そもそもAIコーディングを全糖としたエディタであるCursorなどは、
コーディングのあり方を根本から変えつつあります。
遅かれ早かれ、エンジニアのすることは設計、プロンプト、レビューだけになりそう。
僕はそこまで色々課金できないので、
今はChatGPTだけ有料で使っていて、先生のように教えてもらう形をとっていますが、
日に日に精度が上がっているのを実感します。
インフラ側では、一番助かるのはハードウェアのログ解析です。
例えばOS・MWの各種ログの基本的な出力先である/var/log/messagesというログ。
システムドライバ周りのログは調べても中々分かりにくいし、
警告の対応緊急度を判断するのも、
同じOS、同じMWを長く使い続けていないと習熟しにくい。
ログをコピペして(もちろん個体情報など重要部分は伏せて)、
AIに問題点や対処方法を尋ねられるのはかなりの時間の節約になります。
また、プログラミングと同じくスクリプトなどは簡単に作れてしまうし、
書くのが面倒なPowershellのコマンドもワンライナーで作ってもらうと便利。
システム全体で使える部分もあって、
ツールごとの値段の比較、工数の見積もり、
リファクタリングのアドバイス、テストコードの作成、資料作成に至るまで、
活用しようと思えばいくらでも使えてしまいます。
このようにAIが仕事に活用できるようになって、
実際に仕事量や案件単価に変化は出てきているのでしょうか?気になります。
肌感覚として、平易な案件の単価は下がってきているように感じますし、
案件取得の倍率も高まったように思います。
Lancersの、「Python 開発」のような興味あるキーワードを含む案件の新着通知を毎日見ていますが、
例えば「このボリューム・難易度だったら30万円くらいだろう」というものが、
3万円程度で希望されているようなケースばかり。
時系列で変化を見ないとAI登場による影響を推し量れないのがもどかしいところ。
実際にはどうなのだろう?

生成AI画像らしい画像
フリーランス実態調査2024のフリーランス人口と経済規模の増加率を見ると、
2015年~2024年の間に、フリーランス人口が39.1%の増加、経済規模は38.8%の増加となっています。
コロナピークの2021年から比較すると下落しています。
(公式Web) フリーランス実態調査2024
※公式ページ上にあるPDFに詳細情報があります
案件数が分からないですし、もう2年くらいは動向を見ないと結論付けにくいところではありますが、
フリーランス人口が増える割合の増加率と比べて経済規模増加率が低いところを見ると、
倍率は高くなっていそうだ、と考えられます。
フリーランス人口のAI活用はまだ3割未満だそうで、
IT系に限ると約半数が活用している、との情報があります。
そうなるとAIによる生産性の変化はあって当然ですし、
発注側が「フリーランスの人も生成AIを使う」前提で単価を決めてくることは疑いようがないのでは。
ただ、単に副業解禁の潮流やフリーランスという働き方が人気になってきたこと、
またIT活用できる人の労働人口が増えてきたことなどの方が影響は大きそうで、
生成AIによってどうなったかはまだ見えてきていません。
僕の所属する会社が見ている案件情報では、
「人材探しています」よりも「案件探しています」の方が多く、
しかも経験豊富なベテラン人材が結構余っているのが分かります。
これは営業メールにおける人材紹介と案件紹介の単純な割合比較です。
こちらに関しては、人材を紹介する側では、
AIのサポートもあるし経験不足なエンジニアでも早くキャッチアップできて、
早々に活躍しうる可能性が高まっている、という状況が見えている一方で、
案件発注側がどう考えているかが商流が低い立場からはよく見えてこないので、
分析が難しいのが実情。
現実として、AIを活用する基本的なリテラシーさえあれば、
簡易的なシステムやプログラムは作れてしまう。
そんな時代が来ているのは確かであるため、
データでは結論付けるには尚早ですが、
遅かれ早かれ数人のハイスペックエンジニア+自社が抱えている非エンジニアだけでも、
IT周りの問題を可決できるようになってしまうだろうことは想像に難くありません。
2010年頃だったらまだ数百万かかっていたWebサイト制作も、
今や数万円で作れてしまいます。
昔のダイアルアップ接続のような複雑なネットワーク設定も、
今は自動で一瞬で繋げられるようになっているように、
面倒なことや難しいことが簡単になっている部分もあれば、
AI自体の開発やKubernatesなどのオーケストレーションシステムの設計構築、
他システム連携がガッツリ入ったシステムの構築のように、
技術の高度化に伴う、求められる知識・理解力の増大という部分もあって、
求人は二極化が進行しています。
さてこのような状況から導き出されるのは、
短期的には、対人コミュニケーションに長けたマネジメント層の必要性の比重が高まること。
技術者は超ハイレベルな人か、超低単価でも働ける人でないと仕事がなくなること。
です。
プロジェクトマネージャー(PM)のような立場はもうしばらく残るはずです。
多くの関係他者との調整が必要で、それぞれの関係者に力関係や相性もあるし、
それぞれの会社、それぞれの部署が違うツールを使っていて、
それぞれのツールにあった情報のインプットアウトプットをしないといけないため。
このハブとなる立ち位置はAGI的な動きが必要となるので、
Amazon倉庫レベルの標準化を徹底するか、
ヒューマノイドの登場でもない限りニーズは消えないと思います。
一方で、他の中堅~末端エンジニアの居場所が減ることから、
その中でも比較的コミュニケーションに長けた人たちが
限られたマネジメント層のポストに流れ込むので、
こちらもレッドオーシャンになることが予想されます。
資本主義の構造からして、とにかく事業のコストを下げるという圧力は消えないので、
AIに置き換えられるタスクやポジションは早晩置き換えられていって、
残るタスクは大量の安くてつまらないものと、
僅かな高単価ながら高難易度なものに集約されていくでしょう。
AIはデザイナーの仕事をどう変えるか
こちらは僕は門外漢なので、ITエンジニア側と変化の見通しと比べると解像度が低くなります。
今デザイナーをやっているクルタさんと話した内容を考察の元にします。
生成AIはクリエイティブ領域も意外と強い。
少ないプロンプトから生成されるイラストは、
「いかにも生成AIに作らせた」ものが出てきますが、
タッチなどを細かく指定してあげると、結構使えるものが出てきます。
もはや、上手い絵は時間をかけて技術を磨いて時間をかけて製作するよりも、
AIに任せた方がコスパが良くなってしまう。
さらに、ヘタウマな絵やゆるキャラのような「アジのある」絵も、
プロンプト次第で再現できてしまいます。
デザインというものは、僕の理解では、
ユーザーが目的を達成しようとする上で効果的な見た目・構造を作る要素と、
アッと驚かせたり、緊張感やポップさや居心地の良さ、恐怖感などの感情を揺り動かすアートな要素、
という2つの要素が結びついているものだと思っています。
共通しているのは、発信者のイメージを伝えるコミュニケーション要素でしょうか。
分かりやすく伝えたければベストプラクティスに沿ったUIにした方がいいし、
逆に驚きや個性を推したければユーザを振り回してでも、
既存概念を超えた作りやコンセプトとする形の方がいい。
この2要素のうち、
前者の「使いやすさ、伝わりやすさ」を司る要素は、AIの独壇場です。
多くのデザインを学習しているので、平均的なものは瞬時に作ってもらえます。
なので独自性・個性のないデザイナーは淘汰されるのではないでしょうか。
後者のアート要素は、基本的には依然として人間に分があると思います。
ただし偶然性、好み、そしてAI×人間というハイブリッドな要素があるので、
AI化の波と完全に無縁ではありません。
次のパラダイム転換はロボティクスの一般化
AIは大半の頭脳労働をやれてしまいます。
だからITエンジニアリングとデザインは大きな打撃を受けています。
その逆に、ごみ収集、トイレ掃除、農作業、調理、家屋の修繕、介護、看護といった、
質量ある世界への物理的な働きかけが必要で、かつ単純な動作だけでない仕事は、
おそらくまだほとんど影響を受けていないとと思いますし、今後もそのはずです。
企画立案、書類作成、指示系統のようなブレーン部分は置き換え可能ですが、
ボディの方は人間の方がまだ安いからです。
次のパラダイムの転換は、
家庭や店舗のような末端現場に、AIと連携するロボットが出て来るようになったときに起きるでしょう。
ロボットは壊れやすいし、高いし、安全性の確保も難しいので、
導入にはかなりのお金と工夫が必要になります。
安定的な半導体や材料の供給、
標準化されて量産できる生産ライン、
事故を起こさないための細やかな制御と咄嗟の判断基準の設定、
それに、いざ事故が起きたときの責任の所在をどうするか。
ロボットのエネルギー補給をどのようにするか。(充電式or電源ケーブル式)
水分や物理的な衝撃などによる故障の防止、メンテナンス・修理する体制。
などなど、課題が非常に多いので、
これらのハードルを越えるよりも人間の方がずっと安価。
まだしばらくの間はこのパラダイム転換は起きないでしょう。

今年入ってからもっと画像精度が上がってる気がする
(風土舎)ハクナマタタ的働き方
僕らが訪れたAirBnBのオーナーの野口さんは、色々なことをしていらっしゃいます。
宿なのでもちろん、布団の準備といった宿らしいお仕事をされているわけですが、
畑を持っているので農業もしています。
そして雑草を食べてもらうのに、山羊を飼育しています。
また敷地内には、ご自身で作られたピザ窯やツリーハウスがあって、
薪割りから大工仕事までご自身でやられています。
予約制の木工のワークショップなどもやっています。
お客さんにジビエなども調理してお出ししています。
多くの経験からもたらされる教養、様々な人脈から来ていると思われるお話はとにかく面白くて、
野口さんに会いたくてやって来る人も多いでしょう。
スローライフながらあっという間に時間が過ぎてしまいます。
さて、普段、AIの目覚ましい発展に気を張っている身としては、
野口さんの生き方・働き方に圧倒的な強さを感じます。
自然、動物、人間、アートなどを相手とした仕事では、
AIに置き換わられる隙がほとんどありません。
そもそも、やりたいことをやっているからこそ、
AIに置き換える意味がありません。

夏野菜の苗植えとテントづくりを手伝いました
「AIに仕事が奪われたらどうしよう」という恐怖をもう少し掘り下げてみます。
もし自分の今やっている仕事が、やりたくない仕事なのであれば、
それはAIにやってもらった方が当然助かるでしょう。
やりたくない仕事であり、AIに奪われたら困るというのは、
単に収入が減ることへの恐怖です。
もしそうなのであれば、これに対する対処は、
今すぐ楽しいと思える仕事に転職するか、
そのために早急にやりたい仕事を出来るまでの基礎力をつけることです。
そしてその代償は、いずれにしても収入が減ることです。
やりたい仕事が低賃金であるとか、
スキル不足・経験不足が故に給与を低く提示されてしまうといったケースです。
となると、AIに仕事が奪われて収入が減るか、
やりたい仕事を今やって収入が減るかの違いなので、
それなら善は急げです。

焼きマシュマロ最高
次に、もし自分の今やっている仕事がやりたい仕事で、
その仕事がAIに置き換えられてしまうパターン。
これは厄介です。
例えば僕ら夫婦のように、
プログラム開発やデザインが好きでやっているのに、
その仕事だと食っていけない、となると、
選択肢はどうなるでしょうか。
もし圧倒的なスキルがあるのなら、ほぼ問題ありません。
でもそうでないなら、取れる選択肢は以下が考えられます。
- AIに置き換えられにくい、やりたい他の仕事に軸足を移す
- 個性を尖らせた成果をどんどん発信して、直接お金を払ってくれるファンを作る
- お金がなくても問題ない生活を形成して、やりたい仕事は趣味で継続
- 上の選択肢の組み合わせ
1、AIに置き換えられにくい、やりたい他の仕事に軸足を移す
もし他にもやりたいことがあるのであれば、そちらに転職するのも手ですが、
多くの仕事がAIの影響を受けるとなると、
あらゆる仕事で倍率が上がることが予想されます。
いずれにしても高いレベルを求められるか、給与水準が下がることとなるので、
やはりお金ではない価値基準で仕事を選ぶことは避けられず、
頭脳労働だけではないジャンルでも活躍できる素地が必要になるでしょう。
農林漁業でも、接客業や宿泊業でも、ものづくりでも公務員でもいいですが、
やりたい仕事があるならば早期にジョブチェンジした方がよいでしょう。
ただし素人がいきなり参入して成果を出せるかどうかは別の話です。
各業界にそれぞれ競争があるので、簡単ではなくて当然。
競合したくないのなら、ゼロから新しい仕事を生み出すほかありません。
2、個性を尖らせた成果をどんどん発信して、直接お金を払ってくれるファンを作る
ハードルは高いですが、これが今後らしい働き方になると思います。
つまり、自分のファンを作って、
直接自分が作ったものを買ってもらったり、自分に仕事を振ってもらったりする方法です。
雇われる立場ではなく、
自分で仕事を作る・生み出す立場になる、ということです。
ここでは、組織に雇用される働き方と違って、
色んなスキルが求められます。
自分を他者に売り込む、情報発信力や営業力がまず必要です。
そして、お客さんが買いたいと思える水準の仕事レベルや、
人柄、信用力が必要になります。
これらを突き詰めると、
コミュニケーション能力、
好きなことをやる勇気・行動力や傍若無人さ、
苦手な部分を必要に応じて効率化するITスキルは必須です。
セルフマネジメントや経理などもやらなければいけませんので、
外部委託するにしてもツールを使うにしても、コミュニケーションとITは避けては通れません。
信用に関しては一朝一夕で出来ることではないので、
仕事をやりぬく、
手を抜かず丁寧に仕事をする、
嘘をつかない、
ズルをしないといった積み重ねが必要で、
ここには時間がかかります。
間違っても、仕事を放り出してバックレるとか、
不正を働くようなことはしてはいけません。
3、お金がなくても問題ない生活を形成して、やりたい仕事は趣味で継続
FIRE的な考え方です。
とにかく節約・節制して、徹底的に消費を減らして省エネ体質を作ります。
その上で、浮いたお金を早いうちに長期分散積み立て的な投資に回して経済基盤を構築する。
これが実現出来れば、
やりたい仕事の単価や下がったり仕事量が減ったとしても続けていけます。
誤解を恐れずに言えば、やりたい仕事を趣味的にするということです。
ただしこの手段は、
いずれにしても最低限の生活費を捻出できるだけの仕事をしなければならない上に、
複利を活用するために長期間続けることが必須条件です。
歳を取ってからやりたい仕事が奪われてゼロになったらゲームオーバーなので、
早く着手するか、他の方法を取るようにしましょう。
4、上の選択肢の組み合わせ
ここまでに挙げた1~3の選択肢の組み合わせです。
理想を言えば2のように自分個人で仕事を生み出してお客さんが付けば最強ですが、
誰もがインフルエンサーになったりするわけではないですし、
営業、セルフマネジメントや対人業務などは向き不向きも結構あります。
なので、節約と投資をしながら、
個人事業のために勉強したり人脈作ったりブログやSNSやメルマガを発信するとか、
本業がまだ残っているうちにその仕事で得られる知識経験を最大限吸収して、
地域密着での独立に向けた準備をする、とかが具体的な動きになります。
僕が今やっていることは、ほぼこれに当てはまります。
選択肢2が軌道に乗るまでの間に、1と3を進める感じでしょうか。
僕がやたらと節約して、本業でSEを続けながら副業で便利屋をしているのは、
こういったことを念頭に置いています。

のらぼう菜やご近所さんが掘ってきてくれた筍というご馳走

収穫したばかりのスナップエンドウと俺が小川で積んできたセリ
おわりに
飯能では、「半農住まい」と称して、
半分農業が出来る、畑付き物件を売り出しているという話を聞きました。
飯能と半農の掛詞ですね。
徐々に人が増えてきているようです。
公式サイトもありました。
(公式Web) 農のある暮らし 半農住まい
With AI的な働き方というのは、
こうした質量ある世界におけるアナログな仕事と、
AI含む各種テクノロジーを活用する仕事のハイブリッドという働き方になるのではないでしょうか。
AIを活用して、かつ収入も増加させられるのは、
上位数%に位置する、スキルフルな人に限られます。
キリギリス的な人とアリ的な人に分けられるとすれば、
アリ的な人の方が、まだ社会では多く求められますし、その方がラクでもあります。
しかしAIの発展×資本主義体制という未来では、
アリ的な人はかなり厳しい戦いを余儀なくされます。
半農暮らし的な、自分オリジナルの半〇〇暮らしを作っていくのが、
「AIに振り回されるな、AIを振りまわせ」な生き方なんだろうな、と思います。
以上!
モイモイ!

ツリーハウスから見える景色
~おまけ~
(YouTubeリンク) パソコンを振り回せ PV – 中込


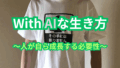
コメント