Moi!
こんにちは、ロニーです。
夏も半分は過ぎたといったところでしょうか。
今回は、ここ数年ずっと自分の中の大きな問題意識となっていたことを書きます。
それが今回のタイトル。
あれこれのテーマをひっくるめて抽象化してしまったので分かりにくいかもしれません。
認知的操作とは何か。
認知には、感覚、知覚、思考、記憶などがありますが、
ここでいう操作というのは、自らが操作するのでなく、
人に操作される、という意味で書いています。
つまり、自分の認知を操作されることへの対処法、です。
今回取り上げる具体としては、
詐欺への対処、情報商材への対処、陰謀論への対処です。
これらに引っかからないようにするために考えることで、
洗脳、フェイクニュースといったものへの見方が鍛えられるはずです。
一個一個のテーマが大きすぎるので、可能な限り簡略に書くことを意識しますが、
そのためやや抽象的になるかもしれません。悪しからず。
認知的操作への対処法について考える
詐欺への対処法
僕は20代の頃に詐欺被害に2度あっていて、トータルで20万円ほど損をしています。
そのため詐欺については以降、よく調べたし、常に意識して気をつけていたのですが、
今年3月にまた引っ掛かりかけたので、正直かなりの危機感を感じています。
今、詐欺被害がかなり増えています。
(NHKニュース記事) 特殊詐欺の被害額 上半期 全国で597億円 過去最悪のペース
詐欺被害の急拡大には色々な要因が考えられていますが、
僕は原因は複合的でありつつも、生成AIの影響が大きいとみています。
嘘を本物っぽく見せることに関してはAIの得意中の得意技です。
脳科学、心理学、行動社会学などの知見を総合利用すれば、人を騙すのなんて朝飯前です。
英語圏の海外に以前からあった様々な詐欺が、
これまでは日本語という壁が防いでいたのが、
AI翻訳によって日本語に訳され、
嘘くさくない、リアルなフィッシング詐欺としてやってきたという見方もあります。
また、普段から騙され慣れていないが故に、
警察や銀行、証券会社、大使館などを騙った詐欺に引っかかりやすい。
なお2024年から、20代・30代の被害が増えているようですが、
若者は情報不足や、恐怖心を煽られるケースが多く、
40代以降は過信を突かれるケースが多いそうです。
僕は両方かも。
(参考)【だまされた人の56%が20〜30代】特殊詐欺被害に関するアンケート調査 SNS世代は「警察官をかたる詐欺」を知らない?若年層に迫る被害
詐欺の手法は多岐にわたります。
なのでここでは個別具体な詐欺への対処方法の紹介は避けて、
要点を押さえておくことにしましょう。
- 自分が主導権を握る
- アクションへの時間を取る
- 第三者に相談する
- お金と情報を渡さない
- 裏付けを取る
自分が主導権を握る
これは、「会話の主導権」を握るという点と、
「判断の源となる情報の手に入れ方の主導権」を握るという2点があります。
相手が誰であろうと、知らない人から持ち掛けられた話は自分の都合で一旦断ち切ること。
考えたり相談したりした上で必要であれば、改めて自分発信で話をすべきです。
詐欺は話を聞いた時点から認知の操作が始まります。
どんなに気をつけていても、
話のキャッチボールの間に少しずつ詐欺に絡み取られていくように構築されているので、
極論、話を聞かなければいい。
持ちかけられた話は無視しても構わない。
降って湧いた話をあたかも「あなたのために」という体でしてくるが、
心当たりのない話なんてのはなかなか起きないし、都合の良い話は全く起きない。
「話を無視したり冷たく接するのは失礼だから…」と
とりあえず話だけ聞いてみようとさせるのが、あちらのやり方。
電話や訪問の営業も大体同じ。
「知りません」か「興味ないです」、最悪無言で切ってよし。
アクションへの時間を取る
当然、相手はあの手この手で話を途切れさせないようにするし、
今すぐに動かないと大変なことになる、
この話を聞かないと損する、
無視したら逮捕される、
今日中にアクションを起こさないと訴えられる…
とデッドラインを作って考える時間や冷静さを奪います。
だからどんな理由でも、まず一旦強引にぶった切る。
そして人に相談したり、裏付けを取ったり、調べたりして、
落ち着いてからアクションを取ること。それが鉄則です。
ちなみにこれも、
訪問販売とか情報商材、ネットワークビジネスへの対策に共通します。
第三者に相談する
詐欺の手口は、茹でダコにされるのに近い面があります。
話をしている間に、徐々にそれもあるかも、本当かもしれない、
と納得させられてしまうのです。
で、引っ掛かった後になって、
「なぜあんな手口に引っかかってしまったのだろう…」と不思議に思うのです。
もっと上等な手口だと、
引っ掛かって損を出してもなお、まだあれは嘘ではないかもしれない、と信じてしまうくらい。
こういったものは、意外に第三者だとすんなり「それは詐欺だよ」と気付けるんですよね。
岡目八目ということでしょうか。
だから他の人から持ち掛けられたら、どんな話であっても第三者に相談すること!
家族でも友達でも同僚でも。
「恥ずかしいから」
「自分で対処できるから」
「口止めされたから」
「人に話したら儲けが無くなってしまうから」
「迷惑がかかるから」…
他の人に話したくなくなるような話ほど、詐欺らしさ満点です。
迷わず相談しましょう。
お金と情報を渡さない
どんな少額でも、どんな口実でも、自分がお金を払わないといけないとなった時点で、
高確率で詐欺確定です。
「後から還ってくるから」
「ローンだから手出しはない」
「全額控除できるから大丈夫」etc…
色んな口実で、損をしないような言い分で、詐欺師は先にお金を払わせようとします。
しかし返ってきません。
敢えて少額出させて、それを一度返して信頼度を高めてから大きいお金を出させる手口も。
海老で鯛を釣る策戦ですね。
しかし直接的だろうと間接的だろうと、びた一文、自分のお金を渡してはいけません。
逆に言えば、
「お金を振り込んで」
「アプリで送金して」
「○○に渡して」
「カードを買ってそのナンバーを教えて」…という、
こちらのお金を払わせる類の文言が出たらほぼ詐欺決定するので、
ここさえ死守すれば結構引き返せるものです。
あと現在は個人情報も取引されるので、
迂闊に自分の住所やカード番号やパスワードを伝えたり入力しないこと。
身分証の写メを送るのも絶対NGです。
※僕は以前騙されてパスポートの写真を送ってしまったことがあります。
パスポート情報が直接使われても、特に大変なことにはならないとされていますが、
何らかの形で悪用されてしまうことは、後からはもう防げません。
裏付けを取る
警察から電話が来たら、別途自分で番号を調べて照会すること。
銀行から連絡があったら、銀行に直接問い合わせること。
気になるメールやSMSやチャット通知が来たら、公式Webサイトを、
ブックマークのリンクから辿るなりググるなりして開いて、内容を確認すること。
「ホンモノの話はネットにはない」
「極秘の情報だから自分しか知らない」
「今は担当者が不在」
「新しいスキームだから誰も知らない」
などと言い分は色々ありますが。
本当か嘘かは、本当である証拠を自分で見つけて裏付けが取れない限り、
「本当ではない」と考える癖を付けましょう。これはめちゃくちゃ重要です。
さて上記の5か条を守れば、詐欺に合う可能性を相当低く出来ると思います。
しかし「怪しいけど5か条に当てはまらないから大丈夫」とは捉えない方が良いでしょう。
常に新しい手口が生み出され続けるのだから。

大きいサギ
情報商材で損をしないために
30代くらいまでの間に、僕は結構情報商材にお金使いました。
まぁいうても、50~60万円くらいですが。(人によっては数百万もつぎ込みます。)
情報商材は必ずしも悪ではありません。
有益な物も当然あります。
しかし詐欺もあれば、ぼったくりもあるし、低品質なものもある。
で、ハズレの割合がやたら高い。
情報商材の提供の仕方は様々ありますが、どんな形であれ、注意が必要です。
PDFや画像ファイルが共有されることもありますし、
動画配信サイトのパスワードを共有する場合だとか、
支払いが済むと受け取れるメルマガもあります。
オンラインミーティング、
レンタルオフィスで開催されるセミナー、
1対1で相談できるコンサルタイプもあります。
情報商材の典型的なやり方としてはこうです。
まずは無料で有益な情報をばらまきます。
お~、これはためになる、とか、面白い、と思わせて、
次は数日~数週間かけてじっくり親近感を持たせます。
毎日届くメルマガとか、LINEグループへの投稿だとか動画を見てもらいます。
単純接触効果とかザイアンス効果といって、
見知らぬ人でも、時間をかけて何度も接することで好印象を持つようになる、
というバイアスを、人は持っています。
だから多少時間をかけて、抵抗感を取り除く期間を与えるんです。
そして「限定」であることを示して、今買わないと損するように思わせます。
〇〇時間限定販売だとか、先着○○名限定だとか、再販はしません、というやつです。
支払いは凄く簡単。高額であれば分割払いやローン支払いでも大丈夫、と受け付けてくれます。
さて、こうしたこうした情報商材、
登録したときや、情報を受け取った段階では満足感があるものです。
ためになったとか、これで自分もお金持ちになれるとか。
でも成果は中々あがらない。出費以上の利益を得られるのはごく一部です。
その原因は様々です。
そもそも完全に嘘の場合がまず一つ。
次に、発信者にとっては儲かる話であっても、
先行者利益しか得られない話であるため再現性がないパターンがもう一つ。
ただおそらく最も多いのは、結局は情報を受け取った人の努力や才能次第であるというもの。
「誰でも簡単にできる」と謳っておいて、
実際には頭金が必要だとか、結果が出るのに時間がかかるとか、
本人が多大な時間を割いて営業や投稿などの労働的行動をしないと結果が出ないケースが典型です。
こういったものだと、
仮にうまくいかなくても、売り手は「本人の努力不足」と切り捨てられますし、
買った方も
「活かせなかったのは自分のせいだからあれは詐欺ではない、嘘ではない」
と自分自身を納得させてしまうんです。
しかし考えてみれば、
その情報商材は「自分に向いていない」商材ということです。
それは結局、無駄遣いと一緒です。
スポーツをしない人がうっかり先走ってスポーツグッズを買いそろえることは中々ないのに、
情報を活かせない人でも、何千円~何十万円もする商材を買ってしまう。
これは良心的なビジネスとは言い難いものです。
ではどう対策すればよいか。
私が根本だと考えている方法は、
「もしその話を全く知らなかったとしたら、
今の、自分の、課題解決のために、その情報商材を自分で調べて見つけ出して買うだろうか」
と考えること。
偶然何らかの形でその商材のことを知り得たがために、
本当はそれまで求めていなかったのに、後付けで欲しいと思わされてしまうのが、情報商材の典型です。
そもそもお菓子、便利グッズ、服など、あらゆる商品が同じなのですが、
全くその存在を知らなければ欲しいとも思わなかったのに、知ったが故に欲しくなってしまった、というのは、これは本来は不要な物だったということです。
他の対策として有効なのは、比較検討すること。
同じような情報がもっと安く手に入らないか。
店頭ではどちらの方がコスパ良いか比較検討するのに、
情報商材となると「これしかない!」と思ってすぐに決めてしまいがちです。
本当に欲しいなら、少し時間をかけてもっと安く手に入らないか頭を使ってみるべきでしょう。
陰謀論への対処法
陰謀論を語る人ほど、「この話は陰謀ではない、真実だ」というものです。
なのでまず陰謀論であるかどうかを決定すること自体が難しいのが、この厄介なところです。
さて陰謀論の種類は様々ですが、ハマらないためには以下のことを押さえておけばよいので、
対応は割合簡単です。
真実かどうかを証明できないものは、真実であると断定できない。
陰謀論やトンデモ話には、共通点がいくつもあります。
その典型が、「真実は隠されている」というものです。
「確かめられないのは、隠されているから」と論者達は言います。
しかし確かめようがないということは、真実とは証明できないということなので、
嘘も本当も五分五分です。
よくあるケースを紹介しましょう。
素性の分からない、あるペンネームAさんが、
「隠されたこの世の真実」とやらを発信しているとします。
この人はAという名前でSNSやYouTube、メルマガで発信しているとします。
そしてこのAさんが支持している某大富豪Bさんがいます。
Aさんは、このBさんの素晴らしさをあれこれ紹介し、
政権中枢やらディープステートやらに通じているというこのBさんが教えてくれた話であるから、
これは真実である、一般人は知り得ることのない隠された情報を私は知ってしまった、
一部のクローズな場でだけ公開できる。
といった類のものです。
よくあるのは、
「この特別な情報は月額5万円のサロン会員だけに伝えます」
といった形で情報商材に持っていくパターンです。
さて、まずAさんの素性が分からないため、ここでほぼおしまいです。
話している内容が真実だろうが作り話だろうが、責任の所在が消えるからです。
仮にAさんと直接会っていたり、Aさんが本名を出していたりしたとしても、
今度はBさんが正体不明です。ここでもおしまいです。
Bさんがどれだけ凄い人で、AさんがBさんをどれだけ尊敬していようが、
Bさんが架空の人物である可能性を排除できないからです。
真実であると証明できない場合は、全てが仮説になります。
仮設の上に仮説を重ねても、全てが砂上の楼閣で、フィクションです。
物語を構成する土台が一つ残らず証明出来て初めて、その論は真実となります。
だから「某大富豪が」「某大統領が」「某学者が」「某経営者が」
「某国の極秘エージェントが」「皇室(とか王室とか)と繋がりのある何某」などといった、
もっともらしい権威付けは論拠の土台にはなりません。
大富豪だろうが大統領だろうが、人間誰しも間違えもするし妄信もするし、
ポジショントークを言うものだからです。
陰謀論が気になるのなら、フィクションとして楽しめばいい。
リアリティがあればあるほど、面白いものです。
ただしフィクションであっても、日ごろから多く接していると、
脳はそれを本物のように受け取ってしまいます。
だからどっぷり浸かるのは避けた方が賢明です。
人は、誰もが、自分が信じたい物を信じ、
不確かな情報は自分でつじつまを合わせて創作してしまう癖を持っています。
だから不確かな情報の断片でも、自分で都合の良い情報を取捨選択し、
ホンモノクサいストーリーを頭に構築してしまうのです。
(参考論文) 陰謀論信念に影響を与える個人要因に対する熟慮的思考の調整機能の検討
(参考図書) ファスト&スロー 上巻・下巻 ダニエル・カーネマン
だから陰謀論に対処するには、
証明できないものは全て、常に「嘘も真実も半分半分」と受け取ること。
そして証明したいのなら、確かな情報を複数突き合わせること。
さらに、反証してみること。
反証とは、「その仮説が真実でないことを示す」ことです。
仮説が絶対に真実ではないと言い切れる証拠があったとき、それは偽であると確定します。
そしてもし「真実でないかどうかが分からない、検証できない」という場合は、
「真実である可能性」があったとしても、
科学ではない、つまり信仰とか宗教の問題になることを示しています。
もし真実であるかどうか分からない、のであれば、
それは嘘であるか、「嘘である可能性があるか」のどちらかです。
これも検証できないのであれば、やはり信じるか信じないかの世界になってしまいます。
多くの話は、確実でにそうであると言い切れないものです。
※以下は超オススメの認知的操作をされないための参考図書です。
科学と宗教の間のスペクトラムを意識する
科学と非科学の境界線は、基本的には「反証可能かどうか」で判断されます。
なので、存在しないと証明できないものは、科学ではなくなります。
一方宗教と非宗教の境界は、実体的な定義でいえば、
「超越的存在、来世、霊的存在を信じる体系であるかどうか」で判断されます。
しかし世の中を広く見渡すと、歴史や考古学のような過去の一度きりの事象に関しては、
知り得る範囲でのエビデンスでしか判断できないですし、推論に頼らざるを得ない面があります。
こういったとき、科学的な手法で判断はするが、最終的にその結果を信じるかどうかは人次第、
という宗教的な面が入り込んでしまいます。
宗教と非宗教の境目もスペクトラム状で、
キリスト教や仏教など、宗教の中でも科学や論理で体系を整理したりします。
そのため、実際には、科学と宗教にバッサリと切り分けられるかというと厳しい。
科学と宗教の間に、歴史とか、哲学とか、芸術とか、占星術などが挟まっていて、
グラデーションになっているため、まずはそうと認識することがまず大事。
その上で、例えば歴史認識、政治、投資予測、環境問題、イデオロギーなどの、
難しい問題を検討していく必要があります。
例えば日本史など歴史を学び、考えるとき。
記録がほとんど失われてしまった過去がどうだったかを考える上では、科学的手法で仮説を立てます。
複数の古文書、遺跡や古墳や発掘された骨や刀剣、土器などの実物を突き合わせ、
さらに神話や口伝などの信憑性が低いものも検討し、
言語体系、民族分布、地層や氷河の積層状態、放射性炭素年代測定など様々な情報を総合して、
最も可能性が高いと考えられる結果を、(現時点の)真実として定めます。
なので時代が変わることによって、
「1192 (いい国) 作ろう鎌倉幕府」が、
「1190 (いい暮れ) 過ごそう鎌倉幕府」に更新されたりします。
(レキシの「歴史ブランニューデイ」より)
絶対・確実な真実を明確に打ち出せることなどほとんどない。
しかし論理や科学的手法を無視して最初から「信じる」というのは安直で、思考停止で、危険です。
おわりに
あまりにも詐欺やフェイクニュースや陰謀論が氾濫している昨今、
受け取る情報に対して、
自分は科学的に判断しているのか、宗教的に判断しているのかをメタに見ることはとても重要です。
風の時代、ディープステート、ユダヤ教レビ族、HAARP、
人工地震、日本沈没、カタカムナ、アトランティス、死海文書、
選挙のハッキング、5G電波による操作、前世と来世、UFOや宇宙人…
怪しい言葉は山ほどあります。それがあっちからもこっちからも聞こえてきます。
真か偽かよく分からない情報が、
さも「確かな情報」であるかのように喧伝されていますが、
「真実かどうか確かめられないもの」は、真実でも嘘でもありません。
「真実かどうか確かめられないもの」は、「真実かどうか確かめられないもの」なのです。
つまり仮説です。
全てを二元論ではなく、その曖昧な状態を曖昧な状態のまま、
状態が変わり得る変数、
もしくは真と偽が重ね合わせになった量子のようなものとしてありのまま飲み込む、
心の広さが必要ではないでしょうか。
それが出来ないのであれば、
これはもやは信仰や宗教の類のものである、と認めた方が無難です。
信仰や宗教の範疇にある物事を、科学的にも真実であると錯覚するのは危険です。
そして宗教であれば、真実であるかどうかは信じる人それぞれのものであるから、
その価値観を他の人に押し付けることはすべきではありません。
そうでないと、現実生活で金銭的損失を被ったり、大事な時間を浪費したり、
家族や友人を失ったりしてしまいます。
生成AIの存在によって、どこまでがフィクションでどこからがノンフィクションなのかが、
非常に曖昧になっています。
目に見えて、声が聞けて、質感を感じられるのに、
全てが虚構という存在があり得るのです。
この傾向は、今後さらに進みます。
そして、そうした状態を逆手に取って、
権力者は民衆を認知的に操作しようとするものです。
それが政党間・国家間の競争にとって優位をもたらしたり、
経済的利益をもたらしたり、イデオロギーを強固にできるからです。
勿論お金儲けを狙う人や企業は、他者を認知的に操作して利益を引き出します。
信じたいことを信じるだけでは、先史時代、神話の時代に逆戻りしてしまいます。
歴史は韻を踏んで繰り返します。
かつて古代ギリシャ時代に進んだ自然科学の知見も、
ローマ帝国の崩壊によって民衆の余裕がなくなって失われ、
キリスト教権威のもと数百年の文明進化の低迷が起きました。
世界史を振り返ると、そうした文明の発展と停滞は周期的にやってきています。
今の科学や学問や知性を軽視する傾向、
「信じたいことを信じる」という風潮は、
停滞の世紀の到来を予感させて、僕は恐いのです。
さて、長い文章となりましたが、今回は以上。
折を見て、僕が実際に引っかかった詐欺体験談などの失敗談系の記事も出したいですね。
モイモイ!


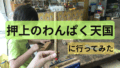

コメント